
2025.10.17
離職率10%減!“女性活躍”を超えて、みんなが楽しく働ける世界をつくる女性社長
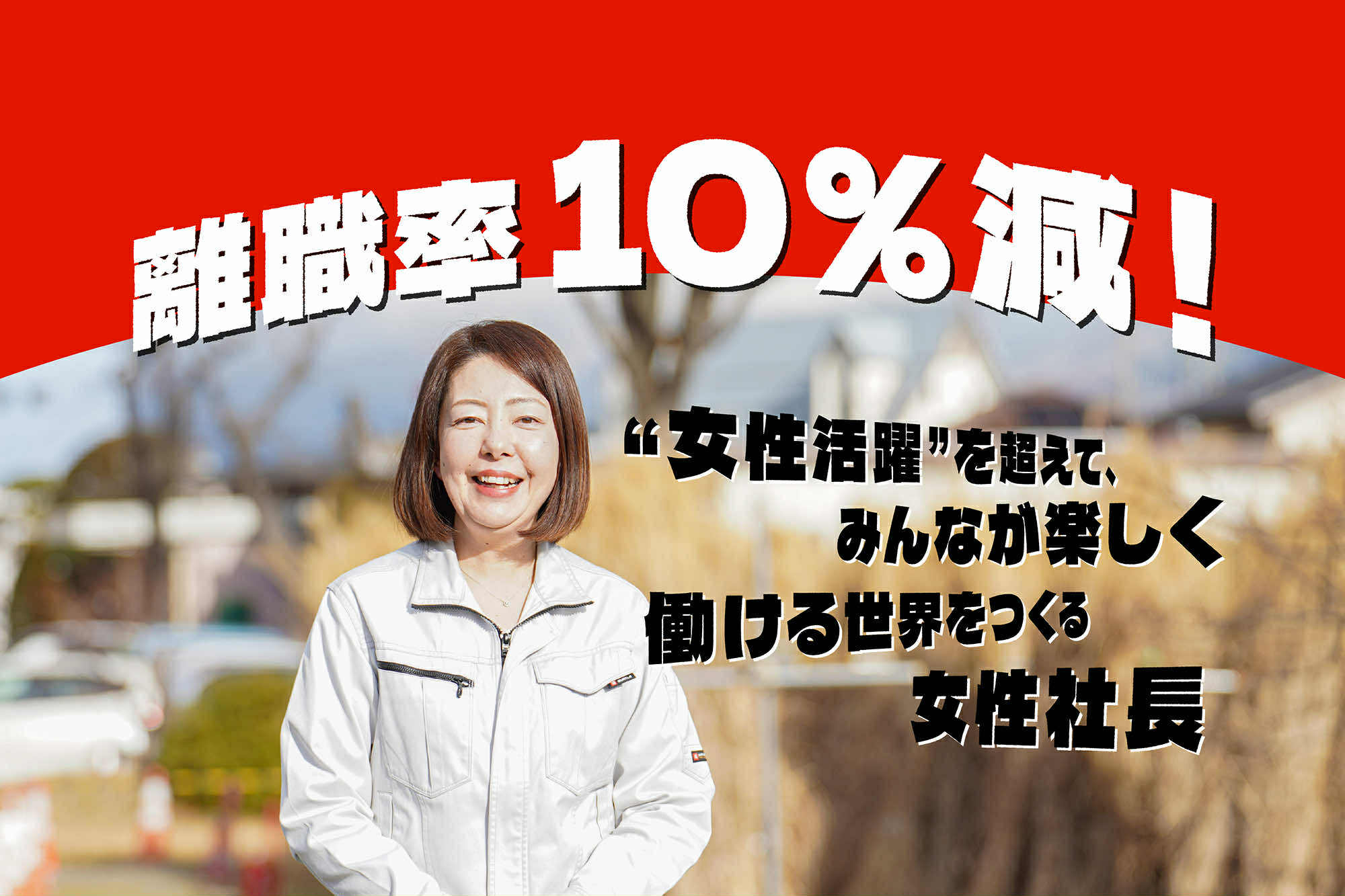
「これからは、女性活躍社会」
「日本は、ジェンダーギャップ指数が世界的に見ても低い」
女性のキャリア形成に関して、そういった声を聞くことは少なくありません。
普段は都内で活動しているライターの僕の場合、新卒入社した会社の上司は女性でしたし、取引先の管理職の方が女性というケースもとても多いです。ただ、それはもしかしたら都市部という環境もあるのかもしれません。
国土交通省が取りまとめた資料(※)によると、就職を機に地方から都内へ転出する女性の割合は男性より高く、「やりたい仕事・やりがいのある仕事が地方では見つからない」という動機が最も高いのだといいます。地方において、女性がキャリアを形成するビジョンがなかなか確立しづらいのが現状だと言えるでしょう。
そんななかでも、長野県には女性が活躍しているシーンが数多くあります。今回、取材したのは長野市内にある高木建設株式会社・社長の髙木亜矢子さん。土木・建築という一般的には“男性社会”だと言われがちな業界のなかで、女性リーダーとして会社を率いてきました。

たとえば、社長就任以前から女性をはじめ離職が多かった職場を改善し、4年ほどかけて離職率を10%近く下げたそう。また、長野県が開催する女性活躍推進会議に呼ばれ、事例を発表したりとダイバーシティを推進しているのだとか。
どのように女性が活躍できる環境を整えてきたのか、お話を伺ってみると返ってきたのが「“女性活躍”と言われると、もどかしい」という答え。その裏側を聞くと、“女性活躍”という考え方を超えた本質的な職場づくりのヒントがありました。
(※国土交通省 国土審議会第5回計画部会 配布資料【資料5-1】地方における女性活躍〜地域がより選ばれるために〜より)
“女性活躍”という言葉が、もどかしい……?

- 小林
- 高木建設は、女性活躍の取り組みを進めていると聞いたのですが、具体的にどんなことをしているのでしょう?
- 髙木さん
- たとえば3月8日の国際女性デーに合わせて全社員に入浴剤をプレゼントしたり、女性のホルモンバランスと食習慣に着目した社内セミナーを開催したり、女子大生との座談会を企画したり。当たり前かもしれませんが、女性用トイレや更衣室の設置も行ってきました。
そうした取り組みから、女性のキャリア形成を推進する企業として長野市の男女参画優良事業所として選ばれたり、将来世代応援企業表彰を受けたり、県内の市町村から女性活躍推進セミナーに呼ばれたりすることも。ただ、あまり“女性活躍”という側面ばかり取り上げられることには、なんだかもどかしい気持ちもあって。

- 小林
- と、いいますと?
- 髙木さん
- 性別も、年齢も、バックグラウンドも、特性も関係なく、あらゆる人と仲間になって働きたい、というのが私の考え。女性はもちろん高齢者の方も働いているし、障がい者の方や、過去に罪を犯してしまった方も雇用して、みんなでいきいき楽しく働きたいんです。
- 小林
- “女性活躍”は、あくまで「みんなでいきいき楽しく働く」のひとつに過ぎないと。
- 髙木さん
- 「女性だから」「男性だから」みたいに「〇〇だから、こうするべき」という前例や思い込みから離れることが、みんなの働きやすさにつながる。高木建設の経営でも、そのスタイルを大切にしています。印象的だったのが、ふと私が金髪にしたい気分になって、20代の社員に「私、金髪にしようかな」って話しかけたんです。そうしたら、その子が「社長が金髪ってやばくないですか!?」ってリアクションしたんです。でも、その直後「いや、今の私の考え、偏見ですよね。『社長=金髪にしちゃいけない』って思い込んでいました」って、自分で気付いたんです。

- 小林
- その人らしさを尊重する風土があるんですね。
- 髙木さん
- とくにうちの会社は、そういった意識を持っている人が何人もいるかも。たとえば、国際女性デーに入浴剤をプレゼントすると決めたとき、もともとは女性だけに配布する予定だったんです。でも、担当していた女性社員から「男性を疎外するのは違うんじゃないですか」って指摘されて。その後、男性にはパートナーや子どもに入浴剤を渡して、日頃の感謝を伝える機会にしてもらう、という企画にしました。

- 小林
- 国際女性デーに、男性も参加できるのか。なんだか高木建設の“女性活躍”って、“全員活躍”の一側面なのかもしれませんね。
- 髙木さん
- そうそう。もちろん意識づくりだけではなく、制度面でもみんながいきいき楽しく働けるような環境を整備してきました。会社では5人以上の社員同士の飲み会や旅行には会社から補助を出したり、婦人科検診や資格取得などに幅広く使える福利厚生制度を設けたり。そんな取り組みを続けるなかで、4年ほど前には離職率が約11%だったのが、2024年には2.2%にまで下がりました。
- 小林
- 4年で離職率が10%近く下がる……!?すごいなぁ。
息子に選択肢を残すため、志した跡継ぎの道
- 小林
- ちなみに、髙木さんが「みんながいきいき楽しく働く」ような世界観を目指すようになった経緯を知りたいなと思うんですが。
- 髙木さん
- 実はもともと私は「女は勉強しなくていい」といった環境のなかで育ってきたんです。

- 小林
- そうなんですか!
- 髙木さん
- もともとうちは女姉妹の家系。祖父の代からいずれ私に夫ができたら、会社を継いでもらう前提で育てられてきました。だから、私も特にキャリアについては深く考えずに学生時代を過ごし、そのまま都内の会社に就職。しばらく経って、好きだったフラワーアレンジメントの世界に入りたいと思って、Uターンし生花店に転職しました。でも、希望していた結婚式の担当に就くことができず、悶々とするなかで1年経たず退職してしまったんです。
- 小林
- その後、家業の高木建設に?
- 髙木さん
- はい。子どものときからこの社屋にはよく出入りしていて、会社敷地内のアスファルトにチョークで絵を描いたり、職人のおじちゃんに遊んでもらったりしていましたし、慣れ親しんでいる環境だからいいかなって。入社後は、品質マネジメントの国際規格ISO9001の管理や、職場環境の改善を担当しました。

- 小林
- 「社長の娘」という跡継ぎ候補とはいえ、「女は勉強しなくていい」という価値観のなかで育ってきたところから、どうして経営者になろうとしたんですか?
- 髙木さん
- たしかに私自身、はじめから社長になろうという意識で入社したわけではありません。そのなかで転機になったのが、息子が産まれたこと。将来、会社を継ぐか継がないかは、本人が決めればいいけれど、もしやってみたいと思ったときの選択肢は残してあげたいと思ったんです。それまで絶対に会社を存続させるんだと心に決めました。
- 小林
- そこから経営者になる道を志した。

- 髙木さん
- どうすれば会社は存続するんだろうと考えたときに、「みんながいきいき楽しく働ける」環境をつくることが大切だなと思って。そこで、女性を含め、社員が仕事に前向きに取り組めるような取り組みを始めるようになったんです。
いきなり状況は変わらない。やるべきことをコツコツと
- 小林
- とはいえ、もともとは「女は勉強しなくていい」という環境だったわけじゃないですか。そこから今のように女性も活躍できるような職場にするのは、なかなか大きな変化だったんじゃないかと思うのですが。
- 髙木さん
- そうですね。私もそれなりに苦労しました(笑)。土木建築業界は、一般的には“男性社会”。正直言うと、当初うちも例外ではありませんでした。飲み会の場では、「いつ結婚をするんだ」「いつ子どもを持つんだ」と聞かれることもしばしば。無茶振りをされて、おもしろいことを言わないといけない、みたいな男性特有のノリにも付いていけなかったこともあります。悪気はないんですけどね。

- 小林
- そこからどのように変化していったんですか?ある意味、悪気はないからこそ、「ハラスメントかもしれない」と省みるようになるのって、なかなか難しいんじゃないかと思うんですが。
- 髙木さん
- まさにそう。私、研修やセミナーを受けるのが好きで、よくダイバーシティなどの職場環境づくりに関するものを受けていたんです。受けた瞬間は「こういう取り組みしたいな!」とモチベーションが湧くんですが、会社で先代に話すと、「そんなものはいい。利益に繋がらない」と一蹴されて、シュンとなってしまうこともあって。
- 小林
- そんな時代もあったんですね。
- 髙木さん
- そんな繰り返しのなかで、「これは自分でやらないと認めてもらえないだろうな」と気付いて。先代には事後報告で、冒頭述べたような職場づくりに関するさまざまな取り組みをガンガン行うようにしました。
- 小林
- 先に実績をつくってしまう。
- 髙木さん
- すると、新聞に載ったり、取引先からも「高木建設さん、いいことしているね」という声をもらったり。社員のなかでも共感してくれる仲間が増えていって、応援してくれたり、社員起点での取り組みが生まれていったりしたんです。そうなってくると、「娘がやっていることは、いいことなのかもしれない」と先代も思い直すようになってきました。

- 小林
- 地道に取り組みを積み重ねていって、社内外に仲間をつくっていくのか。
- 髙木さん
- そう。本当にコツコツ、コツコツ。いきなりは変わりませんからね。今でも、協力会社も集まる安全大会ではハラスメント厳禁を徹底するよう繰り返し呼びかけていたり、管理職にはダイバーシティのセミナーに参加してもらったり。ほかにも産業カウンセラーに入ってもらってお互いのパーソナリティを把握してコミュニケーションに活かせるような仕組みを考えてもらったりしています。
弱さを開示できるリーダーに
- 小林
- 髙木さんは、これまでセミナーに参加される側だったのが、今ではセミナーに登壇する側になっているわけじゃないですか。参加者の方と話してみて、どんなことを感じますか?
- 髙木さん
- みなさん「ロールモデルがいない」と言いますね。特に土木建築の世界は、建設現場に常駐するのが当たり前。その日そこにいる人にそれぞれ担当を決めて進めるのが前提だから、「家族に何かあったらすぐに帰る」というのがなかなか難しかった。

- 小林
- 育児や介護との両立は、たしかに難しいイメージがあります。リモートワークも難しいでしょうし。
- 髙木さん
- そこで高木建設では、工事施工に関係するデータの整理や提出書類の作成などを担う「建設ディレクター」という職種の育成も進めることにしました。それならリモートワークも活用できるし、現場で働く技術職の長時間労働の軽減もできる。実際に、国家資格の施工管理技士を持つ女性がサポーターとして業務を行うことで、現場としても業務を依頼しやすくなります。
- 小林
- それはたしかに新たなロールモデルになりそうです。

- 髙木さん
- ロールモデルがなければ、つくればいい。私も、自分がいかに楽しく働けるかを考えてキャリアをつくってきました。その姿が結果的にロールモデルになったらいいなとも思うんです。
- 小林
- 髙木さんの背中は、たしかにロールモデルになりそうですよね。
- 髙木さん
- 私自身、強くてかっこいい社長みたいなイメージではなくて。社員に悩みを打ち明けるし、叱られちゃうことだってある。でも、そうやって上から目線じゃなくて、ちゃんと弱さも開示できるリーダーでありたいと思うんです。

- 小林
- 男性社会だと「強くあらねばならない」という考え方が根強いと思うので、弱さを開示できるリーダーという視点はたしかに新たなロールモデルかもしれませんね。今日はありがとうございました!
まとめ

「女性活躍」という文脈で取り上げられることが多い高木建設。でも、それは結果論。
性別や年齢、バックグラウンドに関係なく、みんながいきいき楽しく働けるように、それぞれの前にある障壁を一つひとつ丁寧に取り除いていく。そんな地道な取り組みを続けてきた成果なんだと思いました。
自分以外の人が、どんな障壁に向き合っているのか。そこに思いを馳せて、一緒に取り除くことができれば、きっとその人はもちろん自分自身も働きやすい環境が育まれていくはず。そう感じた取材でした。

